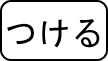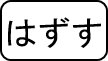-
カテゴリ:校長ブログ
心を一つに最高の舞台へ!音楽会を開催しました。 -
12月5日・6日の2日間にわたり、音楽会を行いました。
今年の音楽会のスローガン

5日の児童鑑賞日には、久しぶりに全学年が体育館に集まりました。

お互いの演奏を聞き合うことで、音楽の楽しさや表現の違いを感じ合う、貴重な時間となりました。
どの学年も、これまでの練習の成果がよく表れた素晴らしい演奏でした。
6日は、保護者や地域の皆さまに向けた発表を行いました。
たくさんの方々の前で演奏することは、子どもたちにとって少し緊張もありましたが、演奏を終えた後の表情からは大きな達成感が感じられました。
また、音楽会の運営にあたっては、学習ボランティアの皆さまやおやじの会の皆さまなど、多くの方々にご協力をいただきました。心より感謝申し上げます。
公開日:2025年12月09日 14:00:00
更新日:2025年12月15日 15:01:45
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 3/21号 ~ 校長blog 最終回 ~ -
校長blog 最終回
2年間に渡り組織目標として取り組んできた「子どもの文脈で学習できる単元開発」も1つの節目を迎えます。
今まで、学年協働によるこの取組によって、授業が変わり、子どもの学びが変わりました。
教育は常に変革しなければ、発展することはないでしょう。
「子どもの文脈で学習できる単元開発」は、永遠の課題です。そしてそれは、「自立した学び」を実現します。
よって、今後も授業の根底にあり、方法は変えながらも常に子どもたちのオーセンティックな学びにチャレンジしてまいります。
とにかく「三小は楽しい!」
時代が変わっても常に子どもたちがそう思えるように、三小は教職員一丸となって取り組みます。
「自立した学び舎 三小スタイル」は今、地に沈め、根となって新たな芽を出し、いつしか花を咲かせます!
公開日:2025年03月21日 07:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 3/14号 ~ 小さな善行賞 ~ -
小さな善行賞

三小恒例の青少対主催「小さな善行賞」を3月4日に行いました。
青少対会長の 師橋 千晴 様 より表彰していただきました。

善い行いには大きいも小さいもありません。
子どもたちの中には、みんなの前で表彰されたいと思っている子がたくさんいます。
褒められることは悪いことではありません。称賛されることで次も頑張ろうという気持ちになります。
大きな大会で優秀な賞をおさめたことは、とても素晴らしいことです。
この小さな善行賞も素晴らしいことなのです。



自立した学びには、評価が大切です。自己評価、相互評価もそうですが、教師から称賛される言葉、評価は次の学びの原動力となります。
1日家庭教育学級で田中副校長が講師を務め、その話の中にあった魔法の言葉。
子どもは褒めて伸ばすことが第一です。
公開日:2025年03月14日 15:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 3/7号 ~ Math Week ~ -
Math Week (算数全校縦割り単元開発)


全校の児童が、同じ時間に同じ教科、単元において、自分の文脈で学習できる単元開発をいたしました。
算数科の図形単元を5時間の計画で、学習環境と学習の手引きをもとに、子ども一人一人が自分で計画を立てて学習を進める単元内自由進度学習の要素を取り入れた開発単元です。



各学年の基礎と発展が準備されており、自己の学年の発展ができれば、次の学年の基礎を学ぶことができます。
そこで、異学年との必然的な協働的な学びが生まれるのです。


内容は、ハンズオンマスを活用し、数学的操作による作業を通して学習するものです。
算数の楽しさを感じさせることも大きな目的です。









2月26日には、このハンズオンマスを創られた玉川大学 教授 柳瀬 泰 先生にも授業を見ていただき、これからの算数の教科としての授業の在り方について、ご示唆いただきました。
この縦割り算数単元開発は、教員のアイデアで生まれました。
三小には、未来の授業を創る先生方ばかりです。
これからも三小の先生方は、子どもたちに生きて働く力を育む真に楽しい授業を創り続けます。
公開日:2025年03月07日 15:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 2/28号 ~ 3学期の単元開発 No.6 ~ -
3学期の単元開発 No.6 6年のマイプラン学習

6年生は、小学校生活の集大成として、算数と理科のまとめの単元をもとに単元内自由進度学習の単元開発しました。
1月28日から3月11日まで、学習の手引き、学習環境をもとに、自分で計画を立てて長期プランで自分の力を伸ばします。
この学習の手引きは、6年生ならではの王道のものでしょう。

各教室や算数教室、広い廊下等、三小の校舎環境のよさを十分に生かした学習環境です。



顕微鏡で学習を進める子どもたち
このスペースも三小ならではの学習環境です。
6年生のマイプラン学習の学びは、三小の集大成として、これからの中学校生活で必ず生かされます。
子どもたちは、最高の力を身に付け、これからの未来をたくましく切り拓いていくことでしょう。
公開日:2025年02月28日 15:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 2/21号 ~ 3学期の単元開発 No.5 ~ -
3学期の単元開発 No.5 5年のマイプラン学習

5年は、国語「もう一つの物語(書く)」と算数「帯グラフと円グラフ」の2教科2単元を組み合わせた単元内自由進度学習の単元開発を行いました。
<5年国語の学習の手引き>
とてもユニークなのが国語の物語文を作成する学習です。
「小説家コース」を基本として、物語文をつくる学習を計画して進めます。「令和の文豪コース」「プロ作家コース」は、更に表現力を高める「技」に視点を置いて、子どもたちに関心をもたせています。どのコースでも子ども一人一人に問いをもたせながら、自分の文章力、表現力を高めたい目的に応じた学習の手引きになています。
また、このコース選択は、3年が開発した国語のマイプラン学習とも系統があるところもこれからの学年の系統性をもった単元開発に有効です。


学習環境の工夫で、子どもたちは自分の力を活用し問いをもち各コースの学習を進めています。
<5年算数の学習の手引き>
算数では、習熟度の観点で学習プリントを工夫し、個々の状況に応じた学習展開できるように工夫しています。



算数少人数による習熟度別の指導では、そのコースを担当する教員に全て任されてしまいますが、この様に学習環境を設定すれば、学習環境の中で習熟度別に学習を進めることができ、また、必然的な子ども同士の協働が生まれます。
算数の新しい学習展開の一つです。
5年生の学びは、1年間の単元開発により多くの汎用的な力を身に付けました。総合的な学習の単元開発では、農業、工業、水産業、伝統工業のテーマで、1年間探究し、KOKUYOの本社でグループごとにプレゼンをしました。探究したことから自分たちにできることを考え提案します。どのグループもアイデアを出し合い、提案性の高さには驚きました。問いをもち、考え、具体策を立てて、実行し、検証する。生きて働く力が身に付いています。
そのことは、学力調査でも体力調査でも結果に表れています。目に見える学力だけではなく、非認知能力の高まりが、知徳体全てにおいて向上しました。来年度の三小の最高学年、リーダーとしての力を十分に発揮してくれることを確信します。
公開日:2025年02月21日 15:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 2/14号 ~ 3学期の単元開発 No.4 ~ -
3学期の単元開発 No.4 4年のマイプラン学習
4年は、社会「世界とつながる大田区」と算数「直方体と立方体」の2教科2単元を組み合わせた自由進度学習の単元開発をいたしました。
4年の学年担任は、2学期に研究発表でも理科で学習環境を工夫し、設定しましたが、そのノウハウをうまく生かし、今回のマイプラン学習の単元を開発しています。

社会の学習環境コーナー

算数の学習環境コーナー
算数の学習の手引きでは、履修すべきことが全て網羅され、かつ、個に応じてステップが踏めるように工夫されています。全員一律に同じ時間に同じ内容を学習るのではなく、自分の問いにあわせて、仲間と必然的な協働を図り、真の問題解決が実現できます。
「先生チェック!」で一人一人の学習状況を学年担任が把握できるので、どの子どもにも単元のねらいを達成できるように指導の個別化が図れるのです。
また、「追加課題」「発展」も準備してあり、それに応じた学習環境に変容していきます。
まさに生きた学習環境なのです。



社会においても個々の問いを引き出し、学習環境の中から自分で学習方法を選択できるように工夫しています。
学習方法の選択こそが、個別最適な学びの第一歩です。
社会においても発展として「チャレンジ」を3つ選択できるようにしています。
まさに、パフォーマンス課題です。
この単元で身に付けた力を活用して汎用性のある力に転換する仕掛けなのです。


情報を共有する工夫があり、学習環境上で個々の考えを共有します。


4年生の学びは、この1年間の単元開発より真の自立した学びを実現できました。
これから高学年の仲間入りをするとともに、何事にも自分事として捉え、主体的、協働的に学校生活を楽しむことができます。
公開日:2025年02月14日 15:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 2/7号 ~ 3学期の単元開発 No.3 ~ -
3学期の単元開発 No.3 3年マイプラン学習
3年は、国語「たから島のぼうけん(書く)」 算数「三角形」の2教科を組み合わせたマイプラン学習を開発しました。

国語は、書く単元を「絵本」か「小説」の2つのコースで選択させて、学習に取り組ませています。
物語を創造して作文をするのですが、学習の手引きで教科書の内容に合わせた手順のプリントを用意し、子どもたちは、絵本作家や小説家になりきって、自分の作文を創り上げます。
ただ単に書くことを目的とした学習ではなく、創作する意欲や創造性を引き出すことに焦点化しています。
また、書き終われば渡島ではなく、発展的な課題も自分で選択できるようにしています。
まさに学習の個性化です。

子どもたちの知的好奇心をくすぐるアイデア
教師の遊び心が満載です。

算数では、富士山コース、エベレストコースの2つの学習を選択します。
算数的活動を取り入れて学習環境を設定しています。

コンパスをつかってかく等の「お試しコーナー」
算数にも発展的な内容があり、個に応じた展開を保障しています。


発展的なパフォーマンス課題も準備されており、個に応じて自分の力を十分に伸ばす学習環境が工夫されています。
3年生のマイプラン学習では、教科の中でもさらにコース選択できる工夫がありました。子どもたちの学びは、オーセンティックです。
公開日:2025年02月07日 14:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ 1/31号 ~ 3学期の単元開発 No.2 ~ -
3学期単元開発 No.2 2年マイプラン学習




2年生からは、マイプラン学習は複数教科で単元を組み合わせます。
このねらいは、1つの教科で単元を自由進度にしたとしても同じ単元なので、進度の進み具合が一目瞭然で、進み具合が良くない子どもは、それだけで劣等感をもちます。いくらみんな違って良いといっても競い合ってしまい、自分のペースでじっくり学ぶことにつながりません。そういうことで複数教科を組み合わせるのです。
2年の学年担任が協働して開発した今回の単元は、国語「あなのやくわり」と算数「はこの形」です。
国語7時間、算数5時間の12時間を自分で計画を立てて学習します。
学習の手引きと学習環境の設定によって、2年生も自立しながら学習します。

学習家核に従って学習がスタート!

教室、広い廊下等、自分で学習するスペースを決めます。

整理された教材

2階の「はこの形」学習環境

自分のペースで、教材を選び、自分で学習を進めます。
1年間の単元開発の授業で身に付けた力で、2年生は、1階と2階を行き来しながら、学習環境のもと学びの目的をもった徘徊をして、自立した学びを実現させていました。
公開日:2025年01月31日 13:00:00
-
カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ1/24号 ~ 3学期の単元開発 No.1 ~ -
3学期の単元開発 No.1 1年マイプラン学習

「自立した学び舎 三小スタイル」~ファースト・モデルの完成を目指して~ として、1年間、メリハリをつけた学習、授業に取り組んでいます。
3学期は、全学年が、1年間、各教科で開発した探究的な単元で、子ども一人一人が身に付けた力を活用して、学習の手引きと学習環境をもとに自分で計画を立てて学習するマイプラン学習(単元内自由進度学習)の単元開発をし、学習に取り組みます。
今週から6週にわたって、各学年の開発した単元をご紹介します。

1年マイプラン学習 算数「かたちあそび」「かたちづくり」
1年生は、算数のなかで図形の単元を取り上げて、「あそび」「つくり」で自由進度をもたせた単元開発をしました。

教材豊富な学習環境

学習の手引きをもとに自分の文脈で学習しています。

形作りに挑戦

いろいろな学習形態を選択できます。


壁面の学習環境をもとにマイプラン学習は進みます。
1年生でもマイプラン学習はよくできます。
本校では、ファーストカリキュラムから一人一人に問いをもたせて探究的な学びを入学当初から進めました。
問題を自分事として捉えて、自分で学習の計画を立てて進めることもこの1年間で身に付けた大きな力なのです。
教師は、1年生のための学習の手引きと学習環境を設定しました。
三小の1年生としての自立した学びが実現できました。
公開日:2025年01月24日 19:00:00