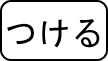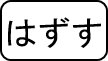カテゴリ:校長ブログ
三小校長ブログ12/6号 ~ 理科の実験を考える ~
~ 理科の実験を考える ~

今までは理科の実験というと理科室でグループごとに同じ条件で同じ実験をし、データを集めてグループで考察する。そのような授業が展開されていたのではないでしょうか。
そのような実験も悪くはありません。
グループで研究仮説を立てって、先生の指示に従って実験の道具を順番に取りに来て、先生が陣日の手順を説明し、その通りに実験を始める。修了すれば、時間内に片づける。実験成功。授業の時間通りに終了。素晴らしい授業です。
しかし、この流れるようなレールを敷いた授業で、どれだけの子どもたちが問いをもち、探究的に学習を進めたでしょうか?
グループの中心となって道具を操作した子どもはそうかもしれませんが全員ではないでしょう。
11月29日の研究発表会で公開授業をした5年生の理科の実験は違います。
単元開発した「もののとけ方」では、一人一人が問いをもちそれに合わせた実験を個人や協働研究するのです。
協働研究と言っても最初からグループが決まっているのではなく、一人一人の問いを掲示板に示し、同じ問いをもった者同士が必然的に協働できる仕掛けがあるのです。

一人一人の問いを共有し、必然的な協働を生む学習掲示

この学習環境こそが、子ども一人一人の探究心を生み出します。
そしてこのように一人一人のニーズに合わせた道具や材料を先生方は、タイミングよく設定するのです。



見事な授業でした。
まるでどこかの製薬会社の研究室のようでした。
1時間完結の流れるような理科の実験も良いですが、これからの社会を生き抜く子どもたちの一人一人の資質・能力を育むのは、どちらの授業なのでしょうか?
公開日:2024年12月03日 07:00:00